
今回はこんな悩みに答えます。
この記事を書いた人
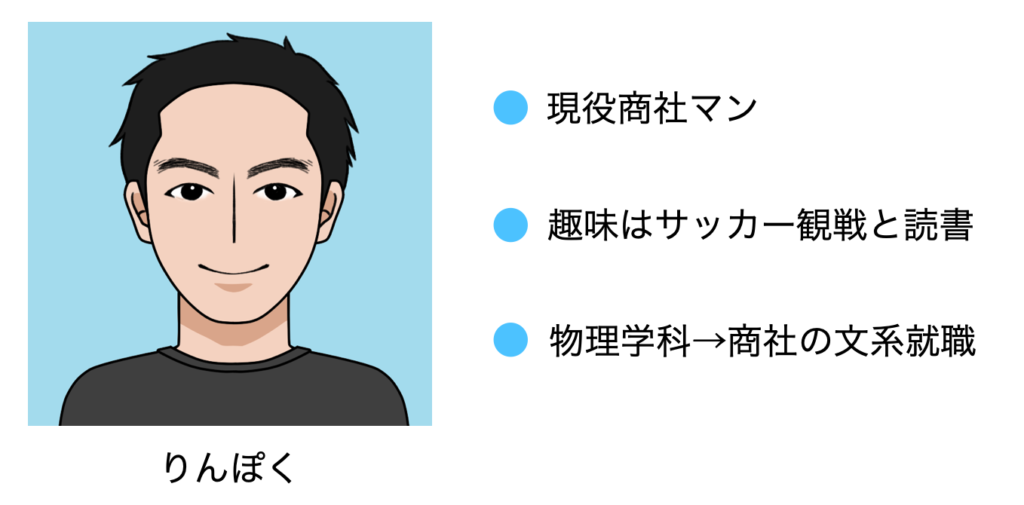
目次
ESや面接でよく詰まる”自分の将来像”

「あなたの将来像を教えてください」
就活をしていると、誰もが必ずされる質問だと思います。人によっては、一番答えにくい質問かもしれないですよね。
とにかく今この瞬間に必死で「将来像なんて全く思い浮かばない!」という人も多いと思います。
そんな学生さんの悩みを解決するために、今日は将来像の考え方について解説します。前半で面接でこの質問が使われる意図を、後半では将来像を考えるときに必要な視点を紹介しているので、ぜひ読んでみてください。
企業が「将来像」を尋ねる意図

そもそも、企業があなたの将来像を尋ねるのにはどのような意図があるのでしょうか?
大きく分けると以下の2つについて確認するためです。
将来像を尋ねる意図
①学生の方向性を知りたい
②学生の意欲や成長性を確認したい
順番に見ていきましょう。
① 学生の方向性を知りたい
まず企業側としては、学生の方向性を確認したいという意図があります。明確でなくてもいいので、学生が将来どのようになっていたいと考えているか把握しておきたいのです。
その際、
「技術職として長く経験を積みたい」
「なるべく早くマネージャーになってプロジェクトを取り仕切りたい」
などの漠然とした形で構いません。
というのも、企業の方向性と極端に外れていないこと確認したいからなんですね。
学生の方向性が100%マッチすることを求めているわけではありませんが、さすがに企業の方向性と正反対だったら入社してもお互い辛いのが目に見えてます。
このようなリスクを避けるための意図だと考えてください。
② 学生の意欲や成長性を見たい
将来像を聞くことで、学生の意欲や成長性を確認したいという意図もあります。
もちろん人それぞれですが、将来像を聞くことでどれだけの意欲や成長性があるか、ある程度企業側は把握できます。
これは具体的であれば良いという話ではなく、学生が自分の現状を把握した上で将来を見据えていることが重要です。ぼんやりとした将来像でも、今の自分がどのようにそこにつながるかを考えられている学生は評価されやすいです。
企業側としても、せっかく採用するなら意欲がや成長性が高い学生の方が良いですよね。テンプレート見たいな答えをしていると、ここで弾かれます。
メモ
いくら具体的な将来像を持っていても、自分の言葉じゃなかったり無理やり作った感が透けて見えると評価が落ちるので気をつけよう。
将来像の答え方は注意が必要

面接では企業側の意図を組むように答えることが重要です。ただ、何も考えずに思い浮かんだ将来像を話すことは多少リスクが伴います。そのことについて、解説します。
就活で話す将来像は明確でなくても良い
さて、いきなり本末転倒な感じですが将来像は明確でなくてOKです。
「いやいや、質問されてるんだからそんなわけないじゃん」
と思うかもしれませんが、本当です。
上記でも述べたように、面接官が知りたいのはあくまで方向性です。具体的に就活生が将来像を思い描いているかどうかについては、そこまで重要視していません。
相手側も、学生でそこまで明確な将来像を思い浮かべるのは難しいことはわかっているんですね。なので、難しく考えずに最低限の方向性を決めて、あとはぼんやりとしたイメージを伝えれば面接官も分かってくれます。
話すときは、最初に「正直に言って、明確なイメージは持っていません。ただある程度の姿で良ければ答えられます」と言いましょう。僕は将来像を聞かれたときは必ずこの答え方をしていました。実際にそれで内定もいただけたので、問題ないです。
具体的すぎてもリスクがある
逆に具体的に答えすぎてもリスクがあるということを認識しておきましょう。ここでいうリスクは以下の2つのパターンです。
将来像が具体的すぎるときのリスク
パターン1:無理して具体的に作ったことが面接官に見抜かれる
パターン2:自分の抱いている将来像が企業側と全く合わない
パターン1に関しては、無理して具体的に将来像を考えたせいで不自然さが出て、それを面接官に見抜かれて評価が下がるというパターンです。
逆にパターン2は、しっかりと考えて具体的な将来像を持っているのにもかかわらず、それが企業の方針と合わない場合です。例えば、ひとつの職種でじっくりと経験を積みたという学生の将来像に対して、企業側は1、2年でのジョブローテーションを想定している場合などですね。
これ、実は危険なのはパターン2の方です。というのも、合わないという理由で落とされる可能性が高いからです。
学生がしっかりとした将来像を持っているにもかかわらず企業の方針に合わない場合、入社した後に摩擦が生じてくる場合が多いので初めから採用しないといこともあります。
なので、具体的な将来像を持つことは素晴らしいことですが、企業の方針と一致しているかどうかあらかじめ確認しておきましょう。もし食い違っていた場合、どうしてもその企業に入りたいなら、ある程度ぼやかして将来像を伝える方が良いです。
結果はお察しです。
将来像を考えるときの3つの視点

では最後に、将来像を考えるときのアドバイスをしたいと思います。
この質問は個人に依存する部分が多いので、完全な答えはありません。ただ、以下の3つの視点を意識することは、面接官に伝わりやすい将来像を考えることに役立ちます。
将来像を考えるときの3つの視点
① 会社の役に立っているか
② マネジメント側なのか技術者側なのか
③ 今の自分の気持ちの延長線上にあるか
こちらも順番に見ていきましょう。
① 会社の役に立っているか
まず自分の将来像が”会社の役に立っているか”という視点を忘れないようにしましょう。これが一番重要な視点です。
あくまで面接は、あなたが将来も会社に貢献してくれるかどうか見極める場です。将来像を聞いてくる理由も、あなたが目指す未来の姿が会社にあっているかどうか確認したいからです。
ここが抜け落ちていると、自分よがりの姿だけを延々と話すことになり面接官からの評価は微妙なものになってしまいます。
② マネジメント側なのか技術者側なのか
将来、複数の職場を経験して早くにマネジメントする側に回りたいのか、ひとつの物事に集中して技術者として大成したいのかどうか、ざっくりとした考えを持っておくと良いでしょう。
世の中の職種は大別するとこの2つに分かれると思います。
あなたが応募した職種が、今あげた2つのどちらのタイプなのかあらかじめ把握しておきましょう。ここが合わないと、企業側もミスマッチなのかな?と考えてしまいます。
③ 今の自分の気持ちの延長線上にあるか
最後に、自分の将来像が今の気持ちの延長線上にあるかどうか確認しましょう。これは単純に、なぜその将来像なのかと面接官から質問された時に、理由を答えられるようにするためです。
その場の思いつきで考えた将来像だと、自分の現状から解離している場合があります。面接官からしたら「これまでの面接内容からだと、その将来像に結びつかなくないか?」と疑問を抱いてしまうわけです。
なので、今まで面接などでアピールしてきた自分の気持ちの延長線上に将来像があるかという視点を持ってください。
まとめ

では、今回の内容のまとめです。
本記事では就活において頻出の「あなたの将来像は?」という質問にどう答えるか解説しました。まず覚えて欲しいのは
・就活で話す将来像は明確でなくても良い
・具体的すぎてもリスクがある
ということです。
企業側も学生がそこまで明確な将来像を持つのは難しいと分かっているので、ぼんやりとしたイメージでも問題ありません。
また具体的なのは良いことですが、それが企業の方針と合わない場合は落とされる可能性があるので注意しましょう。これらを踏まえた上で、将来像を考える際は以下の3つの視点を持ってください。
将来像を考えるときの3つの視点
① 会社の役に立っているか
② マネジメント側なのか技術者側なのか
③ 今の自分の気持ちの延長線上にあるか
この視点を忘れなければ、面接でも十分通用する将来像を構築できるはずです。ぜひ実際に面接が来るまでに自分なりに考えてみてください。
今回はこれで終わりです。
