
今回はこんな悩みに答えます。
この記事を書いた人
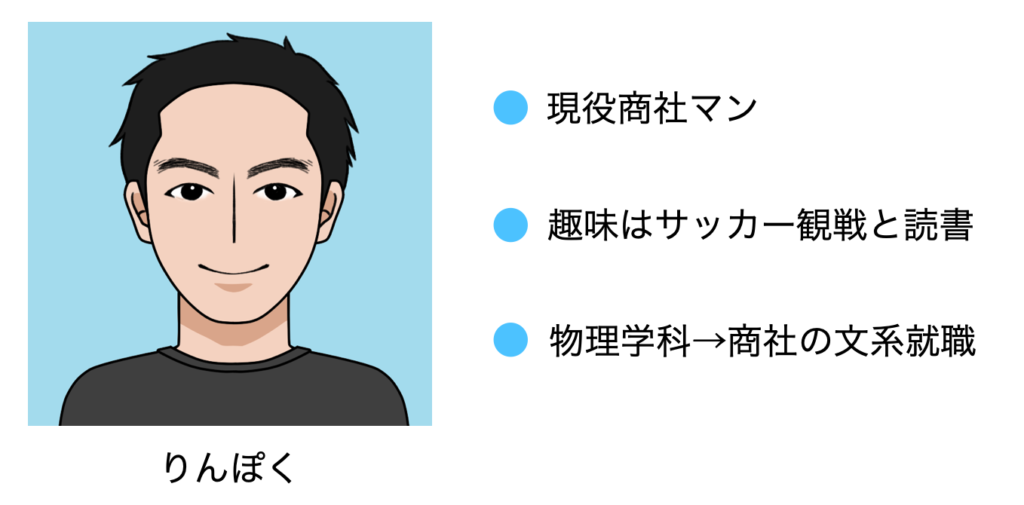
目次
就活の面接で研究内容を説明するのは意外に難しい

就活の面接では、大学での研究内容について聞かれることも多いかと思います。文系の人ならゼミでの研究内容、理系の人なら研究室での研究内容について説明してくださいと言う質問がよくされますよね。
ただ、実際に自分の研究内容を話そうとするとうまく説明できない人はいませんか?
実は、多くの人は上手に研究内容を説明できずに評価を落としてしまっているんですね。自分では詳しく知っている内容であるがゆえに、逆に面接官に伝わりにくい説明になってしまっている場合があります。
ただ、研究内容をうまく話せるかどうかで面接での話の膨らみ具合も違ってきます。
本記事では、面接で研究内容を説明する際に意識することについて解説します。研究内容を説明するのが苦手な人は、ぜひ読んでみてください。
就活の面接で研究内容を説明するときに意識すること
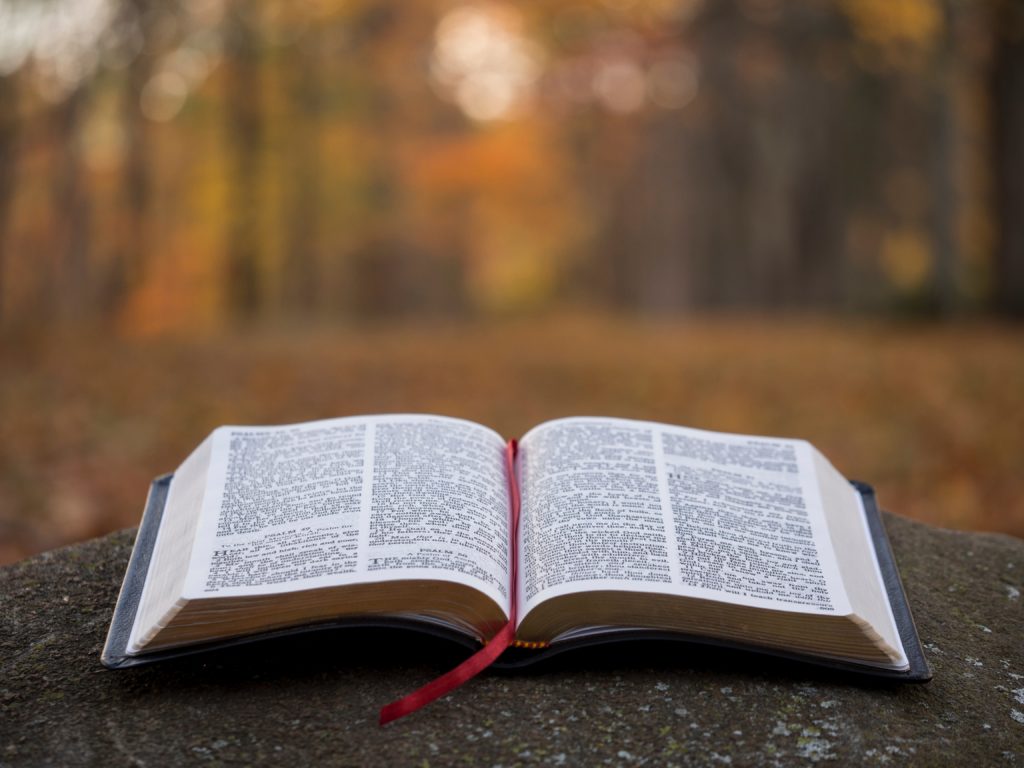
では、就活の面接で研究内容を話すときに意識することを紹介します。
研究内容を話すときに意識すること
① 専門用語は使わない
② 深い内容まで説明しない
③ うまい例を出して理解しやすくする
④ 面接官の理解度を確認しながら進める
上記の4つになります。順番に見ていきましょう。
① 専門用語は使わない
まず最初に大事なことは”専門用語を使わない”ことです。専門用語を使うと、その分野に詳しくない人は一気に混乱して話についていけなくなってしまいます。
意識しないと忘れがちなのですが、基本的に専門用語=外国語だと思ってください。
面接官に話す場合は、なるべく共通でわかる言葉を用いて説明するように心がけましょう。仮にどうしても専門用語を使いたい場合があったら、必ず最初にその意味を説明するようにしてください。
ここを怠ると、面接官にとってあなたの話は全くわからないものになってしまいます。
② 深い内容まで説明しない
次に意識することは”深い内容まで説明しない”と言うことです。
面接で説明していると、ついつい熱心に自分の研究内容の詳細まで語りがちです。
ただし、これは逆効果です。
いくら論理的に筋が通る説明をしようと、内容が濃くなってくると初心者が理解するのは難しくなります。一度でも面接官が話について来れなくなると、それ以降の説明は全く意味のないものになってしまいます。
深く語りたい気持ちはよくわかりますが、グッと堪えて簡単な触りや一般論の説明をするよう心がけましょう。
例えば、あなたが癌の研究をしているとして、面接官に伝える場合を考えみましょう。本当のあなたの研究は、難しい細胞に関するものだったとしても、それを詳しく説明したところであまり理解されません。
それよりは癌のメカニズムの一般論を話して、それに対する自分の研究の位置づけをさらっと伝える方が、面接官からしたら「理解できたな」と言う気持ちになります。
③ 適度に例を出して理解しやすくする
研究内容を説明する際は、いくら説明の筋が通っていても、初心者の面接官にイメージしづらいでしょう。
これを解決するのか"適度に例を交えて話す"ことです。
適切な例え話を説明に取り入れることによって、一気に相手に理解しやすい話になります。僕の経験から行くと、説明が得意な人ほど例え話がうまい傾向があります。
学生がいきなり紳助さんレベルになるのは無理ですが、意識して例え話を入れるようにしてください。徐々にあなたの説明はレベルアップしてきます。
④ 面接官の理解度を確認しながら進める
最後に意識することは"面接官の理解度を確認しながら話を進める"ことです。
1番避けなければいけないことは、面接官を置き去りにして話し続けてしまうことです。こうなると、もはやいくら深い説明をしても無意味になってしまいます。
面接中の所々で、面接官の理解を確認するステップを挟みましょう。
例えば「〜ってこうなりますよね?」みたいな感じで、軽く確認する形で面接官に質問を投げかけてください。
相手の顔を見て、うなずいたりしていたら理解できている。逆に難しい顔をしてたり、イマイチな反応だったら、もう一度簡単に説明を補足する。
このような感じで面接官の理解度を確認しながら説明を進めましょう。これを意識するだけで、面接官を置き去りにするリスクが少なくなります。
小学生でもわかるように伝えることが大事

ここまで研究内容を説明する際に意識することについて説明してきましたが、簡潔にいうと「小学生でもわかるように伝えることが大事」ということです。
面接準備をするときは、常に「この説明で小学生は理解できるかな?」という意識を持ちましょう。そして、なるべく簡潔に伝えられように練習を重ねてみてください。
このような姿勢でいれば、難しい専門用語を使ったり、必要以上に詳しく説明するような事態は避けられます。
また、これは研究内容の説明以外にも言えることです。面接の受け答えの中では、何を話すときも小学生が理解できるレベルで話すように心がけてください。
まとめ:研究内容を詳しく理解させることが目的ではない

今回は、就活の面接で研究内容を説明する際に意識することについて解説しました。
研究内容を話すときに意識すること
① 専門用語は使わない
② 深い内容まで説明しない
③ うまい例を出して理解しやすくする
④ 面接官の理解度を確認しながら進める
研究内容を説明するときは、つい自分目線で説明してしまうので初心者にはわかりにくい説明になりがちです。
上記の4つのことを意識して、研究内容を説明するようにしましょう。わかりやすく研究内容を伝えることができれば、面接官からの評価は確実に上がります。
自己満足で詳しく話すのではなく、小学生でも理解できるように配慮して説明することを心がけましょう。あなたの面接力が一段と高まるはずです。
今回はこれで終わりです。